- 【ハイライト】
- 母との葛藤と絆: 弱っていく母の姿を受け入れられず、ぶつかり、すれ違う日々。しかし、共に過ごす時間の中で、今まで知らなかった母の愛情や、親子の確かな絆を再発見していく。
- 予期せぬ出会いと恋心: 孤独を感じていた健一の心を溶かしたのは、介護者交流会で出会った同世代の女性・明美。同じ境遇で支え合ううち、淡く切ない恋心が芽生えるが、妻への想いとの間で心は揺れ動く。
- 心の成長と変化: 介護という現実を通して、健一自身が変化していく。家族との関係を見つめ直し、人生の後半で見つけた「本当に大切なもの」とは?
- 【導入】
- 定年退職した健一の目の前に突きつけられた、母の介護という現実。慣れない家事、気難しい母との関係、そして忍び寄る認知症の影…。先の見えない日々に戸惑う健一だったが、介護者交流会での「出会い」が、彼の心に変化をもたらす。共感し励まし合う中で芽生えた淡い想いと、妻への罪悪感。揺れる心模様と、深まっていく家族の絆を描きながら、人生の後半に訪れた温かな「ひだまり」を見つけるまでを、優しく紡いでいく物語
第一章:戸惑いの春
「まさか自分が、母親の下着をたたむ日が来るなんてな」
健一は、目の前に広がる洗濯物の山を前に、思わず乾いた笑いを漏らした。桜の花びらが風に舞い、新しい季節の訪れを告げる四月のある朝。長年勤め上げた電機メーカーを先月定年退職し、第二の人生が始まったばかりだというのに、その現実は想像していた悠々自適なものとは程遠かった。定年したら、まずは長年の夢だった北海道へのバイクツーリング、それから書棚で埃をかぶっている歴史小説の読破、時間に縛られず好きなだけ昼寝もしてみたかった。しかし、現実はどうだ。朝早くから起こされ、慣れない家事に右往左往し、そして今、母の下着と格闘している。
リビングのソファには、妻の智子が買ってきた介護入門の本が数冊積まれている。隣町の実家で一人暮らしをしていた母・フミが、軽い脳梗梗塞で倒れたのは退職を目前に控えた冬のことだった。雪のちらつく寒い日で、発見が少し遅れていたら、と医師に言われた時の冷や汗を今でも思い出す。幸い命に別状はなく、麻痺も軽度で済んだが、「日常生活には介助が必要でしょう。独居は難しいですね」という宣告は重かった。施設に入れることも考えた。資料を取り寄せ、見学にも行った。しかし、フミ本人が「知らない人ばかりの所はいやだ。家にいたい」とか細い声で訴え、そして智子が「お義母さん、寂しいのよ。私たちがそばにいてあげましょうよ」と強く主張したことで、在宅介護という道を選ばざるを得なかった。正直、健一には自信がなかった。しかし、仕事にかまけて実家を顧みず、フミに寂しい思いをさせてきた負い目がないわけではない。智子の決意に、半ば引きずられる形で始まった介護生活だった。
とはいえ、健一にとって介護は全くの未知の世界だ。これまで家事らしい家事といえば、せいぜい休日に庭の草むしりをするか、電球を取り替えるくらい。料理、洗濯、掃除、そして何より、身体が少し不自由になり、時折記憶が曖昧になる母とのコミュニケーション。その全てが、重く健一の肩にのしかかっていた。特に洗濯は難物だった。色物と白物、デリケートな素材、お洒落着洗い。智子に言われるままに洗濯機を回すものの、干し方、たたみ方にも作法があるらしい。几帳面な健一にとって、曖昧な指示と勝手のわからない作業は苦痛以外の何物でもなかった。
「あなた、ぼーっとしてないで手伝ってよ。フミさんの着替え、それじゃないでしょ? 今日はデイサービスの日なんだから、少しお洒落なブラウスにしてあげて」
キッチンから智子の少し尖った声が飛んでくる。このところ、智子の声には常に苛立ちが混じるようになった気がする。慌てて手に取った薄紫色のカーディガンを戻し、母の箪笥から指示された花柄のブラウスを探す。箪笥の中には、健一が見慣れないレースのついた肌着や、柔らかな素材のパジャマがきれいに畳まれて並んでいる。こんなものを母が着ていたのか、と妙な感慨が湧く。
「あったぞ、これだろう?」 「そう、それ。早く持ってきてちょうだい」 急かされるままにブラウスを智子に手渡す。フミはソファに座り、少し不満そうな顔で窓の外を見ていた。デイサービスに行くのを嫌がることが増えたのだ。「あんなところ、年寄りばかりでつまらない」というのが決まり文句だった。
介護生活が始まって一月。当初こそ「お袋の面倒は俺が見る」と空元気を振りまいていた健一だったが、現実は甘くなかった。フミは日によって機嫌が大きく変動し、穏やかな時もあれば、些細なことで癇癪を起こすこともあった。特に、自分ができなくなったこと――例えば、好きだった編み物や、得意だった煮物の味付け――を突きつけられると、途端に不機嫌になり、時には健一や智子に辛く当たることもあった。
「あんたたちに、私の気持ちなんかわかるもんか! 丈夫な身体で、好き勝手できていいわね!」
そう言って部屋に閉じこもってしまう母の後ろ姿を見るたび、健一の心は鉛のように重くなった。智子は持ち前の明るさと粘り強さで、「はいはい、わかりましたよー」と受け流しながらも、文句を言いながらフミの世話をこなしていたが、健一は母の気まぐれな言動にどう対応していいかわからず、ただオロオロするばかりだった。昔気質の頑固な父を早くに亡くし、女手一つで健一を育ててくれた母。快活で、少しお節介で、料理上手だった母。その面影は薄れ、今は気難しく、弱々しい老女がそこにいる。その変化を受け入れられず、健一は母との間に、目に見えない壁がどんどん厚くなっていくのを感じていた。
洗濯物をたたみ終え、リビングに戻ると、フミがまだ窓の外をぼんやりと眺めていた。デイサービスの迎えの車が来るまでまだ時間がある。その小さな背中が、やけに寂しげに見える。 「母さん、どうかしたか? 庭のツツジが綺麗に咲いたぞ」 声をかけると、フミはゆっくりと振り返り、虚ろな目で健一を見た。 「……あなたは、どなた?」 その言葉に、健一は息を呑んだ。心臓が冷たくなるような感覚。認知症の兆候。医師からも可能性は指摘されていたが、実際に目の当たりにすると、足元から崩れ落ちるような衝撃だった。 「健一だよ、母さん。息子の健一だ。忘れたのか?」 必死に呼びかけると、フミはしばらく健一の顔をじっと見つめていたが、やがてふっと表情を緩め、「ああ、健ちゃんか。ごめんよ、ちょっとぼんやりしてた。ツツジ、そんなに綺麗かねぇ」と力なく笑った。その笑顔は、いつもの母のものだったが、健一の胸には鉛のような不安が澱のように沈殿した。いつか、本当に自分のことを忘れられてしまう日が来るのだろうか。
その夜、健一は久しぶりに書斎で一人、ウイスキーのグラスを傾けた。智子が寝静まった後、一人静かに飲む酒が、このところの唯一の慰めだった。定年後の生活は、もっと穏やかで、自由で、自分のための時間だとばかり思っていた。それがどうだ。現実は、老いた母の介護と、それに伴う戸惑いや無力感、そして忍び寄る認知症の影に怯える日々だ。これから先、どうなってしまうのだろう。妻との関係も、このままではギスギスしていく一方ではないか。不安と焦りが、春の夜の静寂の中でじわじわと心を蝕んでいくようだった。
「少し、外の空気でも吸ってくるか」 健一はグラスを置くと、音を立てないようにそっと書斎を出て、玄関のドアを開けた。ひんやりとした夜風が火照った顔に心地よかった。見上げれば、朧月が淡い光を投げかけている。住宅街の夜は静かで、虫の声だけが聞こえていた。健一は、この先の見えない介護生活という長いトンネルの入り口に、ただ立ち尽くしているような気分だった。深呼吸を一つして、家に戻ろうとした時、ふと足元に小さな光るものを見つけた。屈んで拾い上げると、それは昼間フミが着ていたブラウスから取れたらしい、小さな貝ボタンだった。なぜだか、その小さなボタンが、今の自分自身のようだと思えた。
第二章:風穴を開けた出会い
五月に入り、風薫る季節となっても、健一の憂鬱な気分は晴れなかった。ゴールデンウィークも、どこへ行く気にもなれず、家でフミの世話と溜まった家事をこなすだけで過ぎていった。フミの状態は相変わらず一進一退で、穏やかな日と混乱する日が交互にやってくる。混乱する日は、特に夜間に症状が出やすく、夜中に突然起き出して「家に帰る」と言い張ったり、亡くなった夫(健一の父)を探し回ったりすることがあった。そのたびに健一と智子は寝不足になり、日中の疲労も相まって、家の中には重苦しい空気が漂いがちだった。
智子は地域包括支援センターのケアマネージャー・田中さんと密に連絡を取り合い、デイサービスの利用日数を増やしたり、訪問看護やヘルパーの手配を進めたりしていた。田中さんは経験豊富なベテランで、親身になって相談に乗ってくれたが、それでも家族が担う精神的、肉体的な負担は大きい。健一は相変わらず介護に不慣れで、食事の介助や排泄の世話などは、どうしても智子に頼ってしまう場面が多かった。
「あなたも少しは介護のこと、勉強したらどうなの? 田中さんから借りた本、読んだの? いつまでも私任せじゃ、こっちが倒れちゃうわよ」 智子の小言も日に日に増え、その声には疲れと諦めが滲んでいた。それは正論であり、健一も頭では理解している。しかし、長年の会社勤めで染み付いた「男は仕事、家事は女」という古い価値観が、なかなか抜けきらない。何より、老いて弱っていく母親の姿を直視するのが辛かった。厳しくも愛情深かった母が、まるで幼子のように自分に頼ってくる。その現実を、健一のプライドが、あるいは息子としての甘えが、受け止めきれずにいたのかもしれない。
そんなある日、田中さんから地域の「介護者交流会」に参加してみないかと改めて誘われた。前回断ったのだが、田中さんは諦めていなかったらしい。 「健一さん、少し息抜きが必要ですよ。同じ立場の皆さんと話すだけでも、気持ちが楽になりますから。奥様にも少しお休みいただく時間を作ってあげてください」 田中さんの言葉は、健一の胸に突き刺さった。智子はずっと気を張っている。自分がもっとしっかりしなければ。 「気が進まないな……」と呟きつつも、「他の方の経験談は参考になるはずよ」という智子の後押しもあり、今度は断らず、重い腰を上げることにした。
交流会が開かれたのは、公民館の畳敷きの和室だった。梅雨入り前の、少し蒸し暑い午後。ドアを開けると、十数人の男女が座布団に座り、テーブルを囲んで和やかに談笑していた。想像していたよりもずっと明るい雰囲気に、健一は少し拍子抜けした。参加者の年齢層は様々だが、皆、どこか共通の苦労を抱えているような、それでいて互いを労わるような温かい空気が流れている。田中さんに促され、健一は部屋の隅の空いている席に腰を下ろした。
自己紹介の順番が回ってきた。健一は緊張で喉が渇くのを感じながら、立ち上がった。 「えー…佐藤健一と申します。先月…いや、もう二ヶ月前か…定年退職しまして、今は妻と二人で、実家で母の介護をしております。母は脳梗塞の後遺症と、少し…認知症の症状がありまして…。介護は全くの素人で、毎日、妻に頼りきりで…戸惑うことばかりです。今日は、皆さんの経験など伺えればと思い、参加させていただきました。よろしくお願いします」 しどろもどろになりながら話し終えると、数人が「お疲れ様です」「最初は大変ですよね」「男手があると助かることもありますよ」と優しい言葉をかけてくれた。張り詰めていた気持ちが、少しだけ解けていくのを感じた。
会の後半、フリートークの時間になった。お茶とお菓子が配られ、参加者はいくつかのグループに分かれて話し始めた。健一は手持ち無沙汰に湯呑みを啜っていた。それぞれのテーブルからは、介護の苦労話だけでなく、工夫していること、利用しているサービスの情報、時には愚痴や笑い声も聞こえてくる。皆、大変な状況にありながらも、前向きに、あるいはユーモアを交えて乗り越えようとしている。その姿に、健一は少しずつ引き込まれていった。自分だけが辛いわけではない。そう思うと、心が少し軽くなった。
ふと、隣の席に座っていた女性が健一に話しかけてきた。年の頃は、健一より少し下、五十代半ばくらいだろうか。ショートカットの髪に、柔らかな笑顔が印象的な人だった。 「はじめまして。私も最近、実家の母の介護を始めたんです。佐藤さんと同じですね」 その声は、澄んでいて心地よかった。 「あ、どうも…」 健一は咄嗟に居住まいを正した。 「私、高橋明美と申します。母が、やはり少し認知症が進んできてしまって…。父は数年前に亡くしているので、今は私が仕事と両立しながら、できる範囲で実家に通っているんです」 「そうですか…お仕事と両立とは、大変ですね」 健一は感心して言った。自分は定年しているからまだしも、働きながらの介護は想像以上に過酷だろう。 「ええ、まあ…正直、きつい時もありますけど」 明美は苦笑したが、その表情は不思議と暗くなかった。 「でも、母の笑顔を見ると、もう少し頑張ろうかなって思えるんですよね。佐藤さんのお母様は、いかがですか?」 「うちの母も、日によって波があって…。良い時は昔の話をしてくれたりするんですが、悪い時は私のことも分からなくなったり…」 健一は、思わず本音を漏らしていた。智子以外の人に、フミの症状を具体的に話したのは初めてかもしれなかった。 「わかります。うちもですよ。昨日できていたことが今日できなかったり、突然怒り出したり。振り回されますよね」 明美は深く頷きながら、共感を示してくれた。 「でもね、そういう時こそ、ちょっとだけ距離を置いて、深呼吸するようにしてるんです。真正面から受け止めすぎると、こっちが参っちゃいますから」 「距離を置く…ですか」 「ええ。母の世界に無理に合わせようとするんじゃなくて、『今はそういうモードなのね』って、少しだけ客観的に見てみる。難しいですけどね」 明美の言葉は、健一にとって目から鱗だった。自分はこれまで、母の言動に一喜一憂し、真正面から向き合いすぎていたのかもしれない。もっと肩の力を抜いてもいいのかもしれない。
その後も、健一は明美と介護の具体的な工夫や、利用しているサービスの情報、時には失敗談などを話し込んだ。明美は聞き上手で、健一の話を優しく受け止め、時折的確なアドバイスをくれた。何より、彼女の持つ朗らかで前向きな雰囲気が、健一の強張っていた心を少しずつ解きほぐしていくようだった。誰かに、こんな風に介護の悩みを正直に話せたのは初めてだった。そして、それがこんなにも気持ちを軽くするものだとは知らなかった。
交流会が終わる頃には、健一の心には春先の陽だまりのような温かさが戻っていた。 「今日は、ありがとうございました。高橋さんとお話しできて、とても参考になりましたし、元気が出ました」 健一は、少し照れながらも素直に礼を言った。 「とんでもないです。私も、佐藤さんの真面目なお人柄に触れて、なんだか励まされました。また、ここでお会いできますか?」 明美はにっこりと笑って言った。 「ええ、ぜひ。また来月も参加しようと思います」 「よかった。じゃあ、また」 明美は軽く手を振ると、他の参加者たちと挨拶を交わしながら会場を後にした。健一は、彼女の後ろ姿が見えなくなるまで、なんとなくその場に立ち尽くしていた。連絡先を交換するような雰囲気にはならなかったが、それで良かったと思った。今はまだ、この交流会という場で、時々話ができるだけで十分だ。
帰り道、健一の足取りは心なしか軽かった。梅雨空の隙間から、束の間の薄日が差している。公民館を出てすぐの公園では、紫陽花が雨に濡れて鮮やかな色を見せていた。介護というトンネルの先に、ほんの少しだけ、明かりが見えたような気がした。それは、高橋明美という女性がもたらした、ささやかな、しかし確かな希望の光だったのかもしれない。家に着くと、智子が少し心配そうな顔で出迎えた。 「どうだった? 少しは気が紛れた?」 「ああ、まあな。色々な人の話が聞けて、少し…うん、良かったと思う」 健一は、明美のことを具体的には話さなかった。なぜかは自分でもよくわからなかったが、今はまだ、自分だけの心の内に留めておきたい秘密のような気がしたのだ。
第三章:深まる共感と淡い思い
交流会での出会いから数週間が過ぎた。季節は梅雨明けを迎え、本格的な夏が始まろうとしていた。蝉の声が日ごとに喧しくなり、強い日差しがアスファルトを焼く。健一の介護生活は、相変わらず試行錯誤の連続だったが、以前のような閉塞感は少し薄れていた。明美の「真正面から受け止めすぎない」というアドバイスを思い出し、フミの言動に一喜一憂するのではなく、少し距離を置いて見守るよう努めた。すると不思議なことに、フミも以前より穏やかな時間が増えたように感じられた。
健一自身にも変化があった。智子に言われる前に洗濯物を取り込んだり、簡単な食事の準備を手伝ったりするようになったのだ。相変わらず手際は悪かったが、その変化に智子は驚きつつも、少し表情が和らいだ。 「あら、ありがとう。助かるわ」 素直な感謝の言葉が、健一には新鮮で、少し照れくさかった。
また、健一は意識的にフミと話す時間を作るようにした。昔のアルバムを引っ張り出してきて、一緒に眺めたり、フミの若い頃の話を聞いたりした。最初は億劫そうにしていたフミも、健一が熱心に聞いていると分かると、少しずつ口を開くようになった。女学校時代の友人との思い出、戦時中の苦労話、早くに亡くした夫との馴れ初め。健一が全く知らなかった母の青春時代の話は、瑞々しく、時には切なく、健一の胸を打った。特に、父との結婚に周囲から反対されながらも、それを押し切って一緒になったという話を聞いた時は、普段気難しく見える母の情熱的な一面に驚かされた。母もまた、一人の女性として、様々な喜びや悲しみを乗り越えて生きてきたのだ。その当たり前の事実に、健一はようやく思い至った。少しずつ、母への見方が変わり始めていた。それは尊敬であり、労りであり、そして深い愛情だった。
そんな変化の兆しが見え始めた七月のある日、健一は駅前のスーパーへ買い物に出かけた。智子に頼まれた牛乳と卵、そしてフミが好きそうな季節の果物を探していると、偶然、見慣れた後ろ姿を見つけた。 「高橋さん?」 声をかけると、カートを押していた明美が驚いたように振り返った。 「あら、佐藤さん! こんにちは。お買い物ですか?」 「ええ、まあ。高橋さんも?」 「はい、母に頼まれたものを少し」 明美はにっこりと笑った。普段の交流会とは違う、私服姿の彼女は、より若々しく、溌剌として見えた。 「もし、お時間があれば、この後少しお茶でもどうですか? 聞きたいこともあって」 健一は、自分でも驚くほど自然に誘っていた。明美は一瞬ためらうような表情を見せたが、すぐに頷いた。 「ええ、いいですよ。ちょうど一息入れたいと思っていたところです」
スーパーの隣にある喫茶店に入り、二人はアイスコーヒーを注文した。窓際の席からは、駅前のロータリーを行き交う人々が見える。 「聞きたいことというのは?」 明美が尋ねた。 「ああ、実は、母のことで少し…。最近、夜中に起き出して徘徊することが増えてきて。何か良い対策とか、ご存知ないかと思って」 健一は、最近の悩みを打ち明けた。明美は真剣な表情で耳を傾け、自身の経験を交えながら、センサーマットの利用や、寝る前の水分の調整、部屋の環境整備など、具体的なアドバイスをくれた。 「でも、一番大事なのは、やっぱり私たち介護者が無理をしないことですよね。夜中に起こされるのは本当に辛いから、ショートステイを上手く利用するとか、家族で交代で夜を見るようにするとか…」 「妻とは、その辺りの分担がなかなか上手くいかなくて…」 健一は思わず弱音を吐いた。 「そうですよね…。夫婦でも、介護に対する考え方や温度差ってありますもんね」 明美は深く頷いた。
それから話は、介護のことだけでなく、互いの家族のこと、趣味のこと、若い頃の夢など、より個人的な事柄へと移っていった。健一は、自分が長年仕事一筋で、趣味らしい趣味も持ってこなかったことを少し恥じながら話した。一方、明美は若い頃にバックパッカーとしてアジアを旅した経験や、今でも続けているコーラスのことなどを楽しそうに語った。健一にはない、自由で柔らかな生き方。その話を聞いているうちに、健一は心が洗われるような気持ちになった。そして同時に、目の前にいる明美という女性に、強く惹かれている自分に気づいていた。それは、友情とは少し違う、淡く、しかし確かなときめきだった。
明美もまた、健一の誠実で少し不器用な人柄に、好感を抱いているようだった。健一が照れながら話す、フミとの最近のエピソード――例えば、一緒にアルバムを見ていて、若い頃の父の写真にフミが「あら、いい男」と呟いた話など――を、楽しそうに聞いてくれた。 「素敵じゃないですか。お母様、きっと嬉しいんですよ、佐藤さんがそうやって関わってくれるのが」 その優しい言葉に、健一は救われる思いがした。
一時間ほど話して、二人は店を出た。 「今日はありがとうございました。また、色々教えてください」 「こちらこそ、楽しかったです。佐藤さんも、あまり根を詰めないでくださいね」 別れ際、明美はそう言って微笑んだ。その笑顔が、夏の強い日差しの中で、やけに眩しく見えた。
この日を境に、健一と明美は、交流会以外でも時々連絡を取り合うようになった。最初は介護に関する情報交換が主だったが、次第に日常の些細な出来事を報告し合ったり、互いの体調を気遣ったりするようになった。まるで、長年の友人のように、あるいは戦場で共に戦う「戦友」のように、二人の間には自然な共感と信頼関係が育まれていった。
健一の中に芽生えた淡い恋心は、日を追うごとに少しずつ輪郭を帯びていった。明美と話していると、心が安らぎ、前向きな気持ちになれる。彼女の笑顔を見るだけで、介護の疲れが和らぐような気がした。しかし、その思いが強くなるほど、健一は罪悪感にも苛まれた。自分には智子という妻がいる。長年連れ添い、今も共に母の介護という困難に立ち向かっている妻を裏切るようなことはできない。それに、この気持ちは、介護という特殊な状況が生み出した一時的な気の迷いなのかもしれない。健一は、自分の心の中で揺れ動く思いを持て余していた。
八月に入り、町内会主催の夏祭りが開かれた。健一は、少しでも気分転換になればと、智子と、車椅子に乗せたフミを連れて会場へ向かった。提灯の明かりが灯り、太鼓の音が響く中、たくさんの人々で賑わっていた。フミは久しぶりの祭りの雰囲気に、少し興奮しているようだった。金魚すくいや綿あめの屋台を眺めながら、ゆっくりと歩いていると、人混みの中に、見知った顔を見つけた。明美が、少し年老いた小柄な女性の車椅子を押しながら、こちらに向かって歩いてくる。 「あら、佐藤さん! 奇遇ですね!」 明美が驚いたように声をかけてきた。隣にいるのが、彼女の母親だろう。穏やかそうな顔立ちの人だった。 「高橋さんも、お祭りに?」 「ええ、母がどうしても行きたいって言うものですから」 明美は母親に健一を紹介し、健一も智子とフミを紹介した。フミと明美の母親は、互いに初対面ながら、「まあ、お元気そうで」「あなたもねぇ」と挨拶を交わしている。智子は、健一と親しげに話す明美を、少し訝しげな表情で見ているような気がした。 短い挨拶を交わしただけで、二組はそれぞれ雑踏の中へと別れていった。ほんの数分の出来事だったが、健一の心は大きく揺さぶられた。智子の視線、明美の母親の穏やかな顔、そして、祭りの喧騒の中で一瞬だけ見せた明美の、少し寂しそうな笑顔。それらが健一の頭の中で交錯し、胸が締め付けられるような思いがした。自分は一体、何を望んでいるのだろうか。
その数日後、フミが熱を出して体調を崩した。夏風邪をこじらせたのか、肺炎の疑いもあるということで、数日間入院することになった。幸い症状は重くなく、すぐに回復に向かったが、健一と智子はその間、病院と家を往復する忙しい日々を送った。健一は、慣れない手続きや医師との面談、そして何より、病院のベッドで弱々しく横たわるフミの姿に、改めて介護の現実を突きつけられた思いだった。
そんな中、明美から健一の携帯に短いメールが届いた。「お母様、いかがですか? 無理なさらないでくださいね」。その短いメッセージが、疲弊していた健一の心に温かく染み渡った。彼は、ただ「ありがとう。大丈夫です」とだけ返信した。それ以上の言葉は、今は見つからなかった。フミの介護に集中しなければならない。明美への個人的な感情は、今は封印すべきだと思った。しかし、彼女からの気遣いが、暗闇の中の灯火のように感じられたのも、また事実だった。
第四章:揺れる心と確かな絆
フミは幸いにも順調に回復し、一週間ほどで退院することができた。退院して家に戻ったフミは、入院前よりも少し穏やかになったように見えた。病院での体験が、何か心境の変化をもたらしたのかもしれない。「健ちゃん、智子さん、ありがとうねぇ。迷惑かけたねぇ」と素直に感謝の言葉を口にすることも増えた。健一は、そんな母の変化を喜びつつ、退院後のケアプランについて、智子やケアマネージャーの田中さんと改めて話し合った。訪問看護の回数を増やし、リハビリも取り入れることになった。健一自身も、以前より積極的に介護に関わるようになっていた。食事の準備や後片付け、入浴の介助の一部なども、ぎこちないながらもこなせるようになってきた。それは、母への感謝の念が、具体的な行動へと繋がってきた証だったのかもしれない。
しかし、母との関係が改善され、介護生活が少し落ち着きを取り戻すと、健一の心の中では、封印していたはずの明美への思いが再び鎌首をもたげてきた。彼女の優しい笑顔、共感してくれる言葉、そして時折見せる寂しげな表情。それらが頭から離れない。この気持ちは、単なる友情や戦友としての連帯感だけではない。もっと深く、個人的な感情だ。しかし、それをどうすればいいのか。智子への罪悪感は消えない。もしこの気持ちを明美に伝えたら、彼女を困らせるだけではないか。今の穏やかな関係さえ壊してしまうかもしれない。健一は、出口のない迷路に迷い込んだような気持ちで、来る日も来る日も思い悩んだ。
八月も終わりに近づいたある日、定例の介護者交流会が開かれた。健一は、少し緊張しながら会場へ向かった。明美に会うのが、嬉しいような、怖いような、複雑な気持ちだった。会場に着くと、明美はいつものように柔らかな笑顔で健一を迎えてくれた。 「佐藤さん、お母様、退院おめでとうございます。良かったですね」 「ああ、ありがとう。おかげさまでね」 健一は、ぎこちなく返事をした。
その日の交流会では、夏場の介護の注意点や、熱中症対策などが話題になった。健一も、自身の経験を少しだけ話すことができた。会の終わり、参加者が帰り支度を始めた頃、明美が健一のそばに来て、小声で言った。 「佐藤さん、もしよかったら、帰り少しだけ話せませんか?」 健一は驚いて明美の顔を見た。彼女の表情は真剣だった。 「ええ、もちろんです」
二人は公民館を出て、近くの公園のベンチに腰を下ろした。夕暮れが近づき、空が茜色に染まり始めている。ひぐらしの声が物悲しく響いていた。 「あの…」 明美が口を開いた。 「夏祭りの時、お会いしましたよね。奥様と、お母様と」 「ええ」 「奥様、とても素敵な方ですね。佐藤さんのこと、しっかり支えていらっしゃる」 その言葉に、健一は胸がちくりと痛んだ。 「まあ…妻には、本当に苦労をかけています」 「…佐藤さん、最近、少しお元気がないように見えたから、心配していました」 明美は、真っ直ぐに健一の目を見て言った。その瞳には、深い優しさと、何かを見透かすような聡明さがあった。健一は、彼女には何もかもお見通しなのではないか、という気がした。
健一は、意を決した。ここで曖昧なままにしておくことは、かえって不誠実だと思った。 「高橋さん…いや、明美さん」 初めて名前で呼んだ。明美は少し驚いたように目を見開いたが、何も言わずに健一の言葉を待っていた。 「正直に言います。私は…明美さんと話していると、心が安らぐんです。介護の辛さも、なんだか乗り越えられるような気がしてくる。それは…単なる友人として、というだけではない気持ちも…あるんだと思います」 言葉を選びながら、健一は自分の気持ちを伝えた。恋愛感情だとは明言しなかったが、特別な好意を抱いていることは伝わったはずだ。 「でも、私には妻がいます。妻を裏切るつもりはありません。それに、あなたを困らせたいわけでもない。ただ…この気持ちを、どう扱っていいのか、わからなくて…」 言い終えると、健一は俯いて、明美の反応を待った。心臓が早鐘のように鳴っていた。
長い沈黙が流れた。ひぐらしの声だけが、やけに大きく聞こえる。やがて、明美が静かに口を開いた。 「…打ち明けてくださって、ありがとうございます、健一さん」 彼女もまた、健一を名前で呼んだ。 「正直、驚きました。でも…健一さんの誠実な気持ちは、伝わりました」 明美の声は、震えていなかった。落ち着いた、優しい声だった。 「私も…健一さんと話していると、心が安らぐんです。介護って、孤独な戦いになりがちだけど、健一さんが同じように頑張っていると思うと、励まされる。それは、私にとっても、とても大切な支えになっています」 彼女はそこで言葉を切り、小さく息をついた。 「健一さんが抱えていらっしゃるお気持ち…それがどういうものなのか、私には正確にはわかりません。でも…」 明美は、健一の顔をじっと見つめた。その瞳は、夕暮れの光を受けて、潤んでいるように見えた。 「私も、健一さんのこと、人としてとても尊敬していますし、大切な友人だと思っています。だから…これからも、こうして時々、話を聞いてもらえたら嬉しいです。お互い、無理せず、支え合っていけたら…そう思います」
それは、健一が期待していたような答えではなかったかもしれない。しかし、拒絶でもなかった。明美は、健一の気持ちを受け止めた上で、二人の関係性を「特別な友人」「支え合う仲間」として続けていきたい、と示してくれたのだ。健一の心の中にあった重い靄が、すっと晴れていくような気がした。そうだ、それでいいのかもしれない。恋愛という形にこだわらなくても、互いを大切に思い、支え合う関係は築けるはずだ。
「ありがとう、明美さん。そう言ってもらえて…嬉しいです。これからも、よろしくお願いします」 健一は、心からの笑顔でそう言った。明美もまた、安堵したように微笑んだ。 二人の間には、恋愛とは少し違う、だが確かな絆が生まれた瞬間だった。それは、介護という過酷な現実の中で見つけた、ささやかで、しかし何物にも代えがたい宝物のような関係だった。夕闇が迫る公園で、二人はしばらくの間、言葉少なに向かい合っていた。吹く風は、もう秋の気配を帯び始めていた。
第五章:秋風と新たな日常
季節は夏から秋へと移り変わった。あれだけ喧しかった蝉の声はいつの間にか聞こえなくなり、朝晩は肌寒さを感じる日が増えてきた。公園の木々も少しずつ色づき始めている。健一の日常は、相変わらず母フミの介護を中心に回っていたが、その表情には以前のような悲壮感や焦りは消え、穏やかさが漂うようになっていた。
明美との関係は、あの夕暮れの公園での会話以来、より落ち着いたものになった。二人は互いの気持ちを確認し合った上で、一線を越えることなく、互いを尊重し、支え合う「特別な友人」としての距離感を保っていた。月一回の交流会で顔を合わせ、時にはメールや電話で近況を報告し合う。話題は介護のことに限らず、読んだ本の話、見た映画の話、あるいは昔の思い出話など、多岐にわたった。健一にとって、明美との会話は、介護生活の中で乾きがちだった心に潤いを与えてくれる、かけがえのない時間だった。
健一の変化は、家庭の中にも良い影響をもたらしていた。以前は介護の愚痴や不満を漏らすことが多かったが、最近はむしろ、フミの面白い言動や、介護の中で見つけた小さな発見などを、ユーモアを交えて智子に話すことが増えた。 「母さん、今日デイサービスでカラオケ歌ったらしいぞ。『青い山脈』を熱唱して、拍手喝采だったってさ」 「まあ、お義母さんったら。元気ねぇ」 そんな会話が、食卓で交わされるようになった。
フミとの関係も、以前とは比べ物にならないほど良好になった。もちろん、認知症の症状がなくなるわけではなく、時折混乱したり、気難しい一面を見せたりすることはある。しかし、健一はもうそれに振り回されることはなかった。母の言葉の裏にある寂しさや不安を、少しだけ理解できるようになったからだ。「また始まったな」と心の中で呟きながらも、穏やかに、時にはユーモアで受け流す余裕ができていた。昔のように言い争うこともあるが、それは一時的な感情のもつれであり、根底には互いを思いやる気持ちがあることを、二人は暗黙のうちに理解し合えるようになっていた。フミもまた、健一のそんな変化を感じ取っているのか、以前よりも健一を頼りにし、甘えるような素振りを見せることが増えた。
智子は、そんな健一とフミの変化を、静かに見守っていた。夫が以前よりも明るくなり、介護にも前向きに取り組むようになったことを、素直に喜んでいた。それが、あの介護者交流会で出会った「高橋さん」という女性の影響であることにも、薄々気づいていたかもしれない。夏祭りの夜、健一が明美と親しげに話すのを見た時の、智子の少し硬い表情を、健一は忘れてはいなかった。しかし、智子はそのことについて、健一に何かを問いただすようなことはしなかった。夫の精神的な負担が軽くなり、家庭の雰囲気が和らいだことを、今はそれで良しとしているようだった。あるいは、長年連れ添った夫の変化の理由を、敢えて深く詮索しないという、妻としての賢明さなのかもしれなかった。健一は、そんな智子の態度に、感謝と少しの申し訳なさを感じながらも、何も言わずにいた。
秋晴れの穏やかな午後。健一は、リビングの窓辺で洗濯物をたたんでいた。春先には、母親の下着をたたむことにあれほど戸惑い、途方に暮れていた自分が嘘のようだ。今では、フミの小さな肌着やブラウスを手に取るたびに、愛おしささえ感じるようになっていた。手際よく洗濯物をたたみながら、ふと窓の外に目をやる。向かいの家の庭にある柿の木が、オレンジ色の実をたわわにつけている。空は高く澄み渡り、心地よい秋風がレースのカーテンを揺らしていた。
健一は、たたんだ洗濯物を箪笥にしまいながら、静かに微笑んだ。定年後の人生は、予想もしなかった形で始まった。しかし、失ったものばかりではない。母の知られざる一面を知り、改めてその愛情の深さに触れることができた。妻との関係も、新たな段階に入ったのかもしれない。そして、明美という、心を通わせられる特別な友人にも出会えた。介護という現実はこれからも続くだろう。フミの症状が進む可能性だってある。しかし、もう以前のような不安はない。支えてくれる妻がいる。励まし合える友がいる。そして何より、自分自身の中に、困難を受け止め、乗り越えていこうとする静かな力が湧いてきているのを感じる。
「健ちゃん、お茶が入ったよ」 フミの声がする。リビングのテーブルには、湯気の立つ湯呑みが二つ用意されていた。フミは、ソファに座り、穏やかな顔で健一を待っていた。 「ああ、ありがとう、母さん」 健一は、フミの隣に腰を下ろした。窓から差し込む午後の日差しが、二人を柔らかく包み込んでいる。それは、健一にとって、第二の人生で訪れた、穏やかで、温かな「ひだまり」のような時間だった。このひだまりの中で、ゆっくりと、自分らしい実りの秋を迎えていけばいい。健一は、湯呑みを手に取りながら、澄み切った秋空を見上げた。その心は、静かな希望で満たされていた。


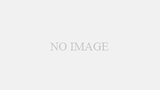
コメント