
「……で、今後の見通しは?」
私の問いかけに、目の前に座る70代の男性は力なく首を振った。資産はある。家族もいる。だが、彼の目には「次」がなかった。ただ、終わるのを待っている目だ。
私はため息を飲み込みながら、認定調査の書類に無機質な数字を書き込む。52歳、独身。仕事は介護認定調査員。毎日、他人の人生の「採点」のようなことをしながら、自分自身の人生は赤点ギリギリのような気がしてならない。
「このままで良いのか?」
最近、夜中にふと目が覚めると、その言葉が天井に張り付いている。
そんな私が、美咲と出会ったのは、冷たい雨が降る晩秋の夜だった。 行きつけの小さなビストロで、彼女は隣の席で一人、赤ワインを飲んでいた。50代半ばだろうか。背筋が伸び、仕立ての良いジャケットを着こなしている。だが、私が職業柄つい見てしまう靴先は、手入れされているものの、かなり履き古されていた。
ふとしたきっかけで言葉を交わした。彼女はフリーランスのランドスケープデザイナーだと言った。
「私、枯れかけた庭を再生させるのが得意なの。植物も人間も、ちょっとした光と水で、驚くほど変わるのよ」
彼女はそう言って笑った。その笑顔は、私が仕事で毎日接する「諦め」の表情とは対極にあった。自立した大人の女性の余裕。私は久しぶりに、胸の奥が少し熱くなるのを感じた。
それから何度か食事を重ねた。彼女との時間は心地よかった。彼女は常に「次のプロジェクト」について目を輝かせて語った。意欲的で、未来を見ていた。
だが、私の長年の「調査員としての勘」が、微かな違和感を訴えていた。
彼女は自分のプライベートをほとんど語らなかった。どこに住んでいるのか、家族はいるのか。私が尋ねようとすると、巧みに話題を庭木の話にすり替える。 そして、彼女の身なりだ。上質なものを身につけているが、どこかちぐはぐなのだ。古い高級時計に、安物のバッグ。
――本当にデザイナーとして成功しているのか?
ある夜、私は見てしまった。 デートの帰り道、彼女を見送った後、忘れ物に気づいて後を追った時のことだ。彼女は、私に告げた方向とは違う、街外れの古いアパート街へと入っていった。そこは、独居の高齢者や生活保護受給者が多く住む、いわゆる「訳あり」の物件が集まるエリアだった。
私の脳内で、冷徹な調査モードのスイッチが入った。 自立した女性? 未来への意欲? ……もし、それが全て嘘だったら?
職業柄、高齢者を食い物にする詐欺師の話は嫌というほど聞いている。ターゲットの信頼を得て、財産をむしり取る手口。彼女のあの明るさ、親しみやすさ。それすらも武器に見えてきた。
「まさか、な」
私は自分の疑念を打ち消そうとした。だが、一度芽生えた疑惑は、黒いインクのように心の中で広がっていく。私は彼女を「調査」することにした。
次の週末、彼女は「大事な顧客との打ち合わせがある」と言った。私はその言葉を頼りに、先日の古いアパートの近くで張り込んだ。
冷たい風が吹く中、一時間ほど待っただろうか。彼女が現れた。 だが、その姿に私は息を呑んだ。いつもの洗練されたジャケットではない。作業着のような汚れた服に、長靴。そして、両手には巨大な園芸用の土の袋を抱えている。
彼女は、築40年は経とうかという錆びついたアパートの、一階の角部屋に入っていった。
私は足音を忍ばせ、その部屋の窓辺に近づいた。カーテンの隙間から、中の様子が少しだけ見える。 そこは、六畳一間の狭い部屋だった。部屋の隅に、介護ベッドが置かれている。そこに、骨と皮ばかりになったような老婆が寝ていた。
私の心臓が嫌な音を立てた。まさか、ここで何をしている?
その時、美咲の声が聞こえた。
「おばさん、見て。今日は良い腐葉土が手に入ったの」
美咲は、老婆のベッド脇に座り込み、泥だらけの手で老婆のシワだらけの手を握っていた。いつものレストランで見せるような、いや、それ以上に柔らかな笑顔だった。
「おばさんが昔、私にくれたお小遣いで買ったアジサイ、覚えてる? あの色が出したくて。今度、ベランダに植え替えるからね。ベッドからでも見えるように」
老婆は、微かに頷き、涙を流しているように見えた。
「……ありがとう、美咲ちゃん。あんたのおかげで、生きていられるよ」 「何言ってるの。私が今こうして仕事ができるのも、全部おばさんが育ててくれたおかげじゃない。感謝してるのは私の方よ」
私は、窓の下で立ち尽くしていた。 冷たい風が、私の浅はかな疑念を吹き飛ばしていく。
彼女は詐欺師などではなかった。 幼い頃に自分を育ててくれた、身寄りのない叔母を、たった一人で介護していたのだ。経済的に決して楽ではない中で、彼女は自分の服や靴を犠牲にしても、叔母の最期の時間を彩ろうとしていた。
自立とは、ただ金を稼ぐことではない。自分の足で立ち、自分の意志で大切なものを守り抜くことだ。 彼女は、感謝の気持ちを原動力に、過酷な現実の中で「次」を見据えていた。「アジサイを咲かせる」という未来の目的を持っていた。
私が調査員として見てきた「幸せな最期」の条件を、彼女は今、この瞬間も実践していたのだ。
私は自分が恥ずかしくてたまらなかった。人の人生を書類の上の数字でしか見てこなかった報いだ。
そっとその場を離れようとした時、バランスを崩して足元の空き缶を蹴ってしまった。 カラン、と乾いた音が響く。
「誰?」
窓が開け放たれ、美咲と目が合った。彼女は驚き、そして私の姿を見て、バツが悪そうに視線を逸らした。
「……見られちゃったわね」
彼女は小さくため息をついた。
「ごめん、嘘ついてて。私、全然優雅なデザイナーなんかじゃないの。これが現実」
私は、泥だらけの彼女の前に歩み寄った。どんな高級なドレスを着ている時よりも、今の彼女が美しく見えた。
「いや、違う」
私は首を横に振った。
「君は、僕が今まで見てきた中で、一番美しい庭を造っているよ」
私の言葉に、彼女はきょとんとし、やがて目元を赤くして笑った。
雲の切れ間から、夕日が差し込んだ。錆びついたアパートのベランダが、一瞬だけ黄金色に輝いた。 私は、自分の人生もまだ、捨てたもんじゃないかもしれないな、と思った。少なくとも、この女性の作る庭が花を咲かせるのを、隣で見届けるくらいの未来は、残されているはずだから。
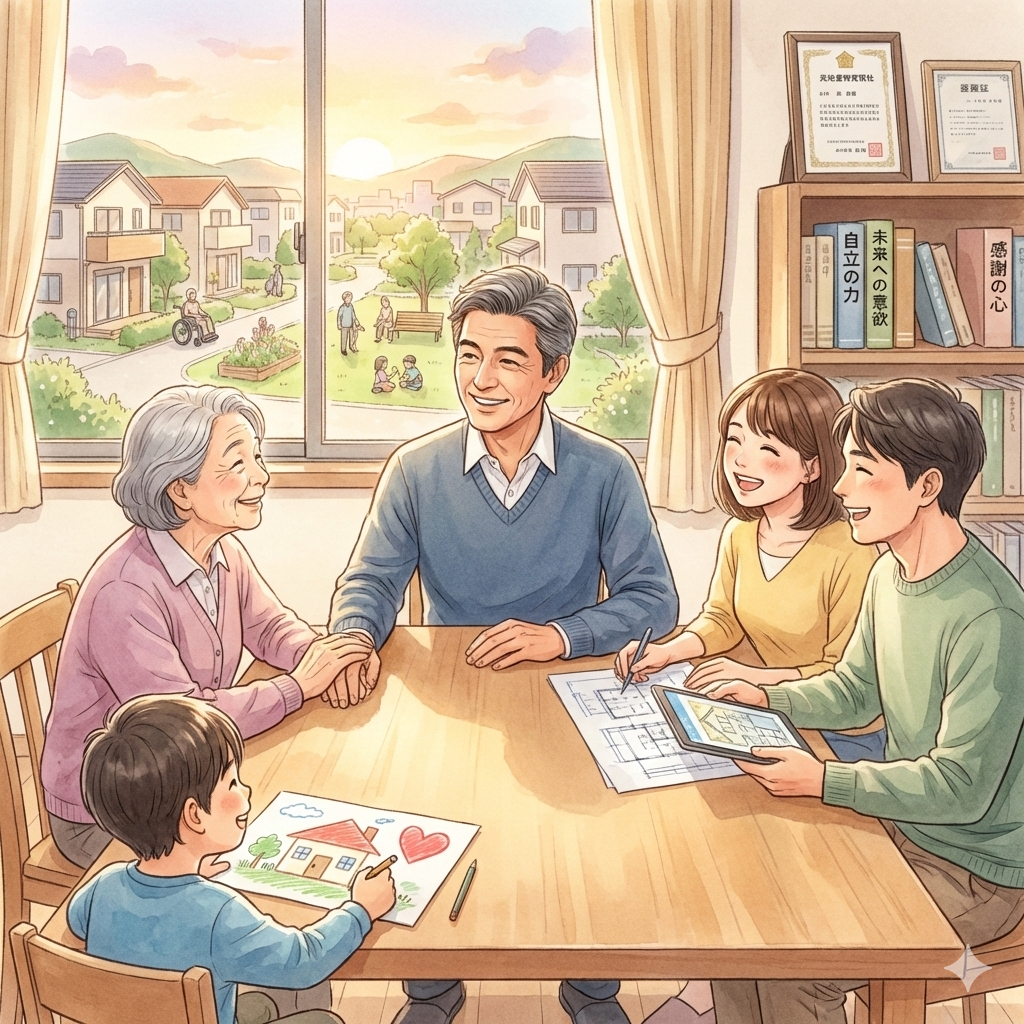
コメント